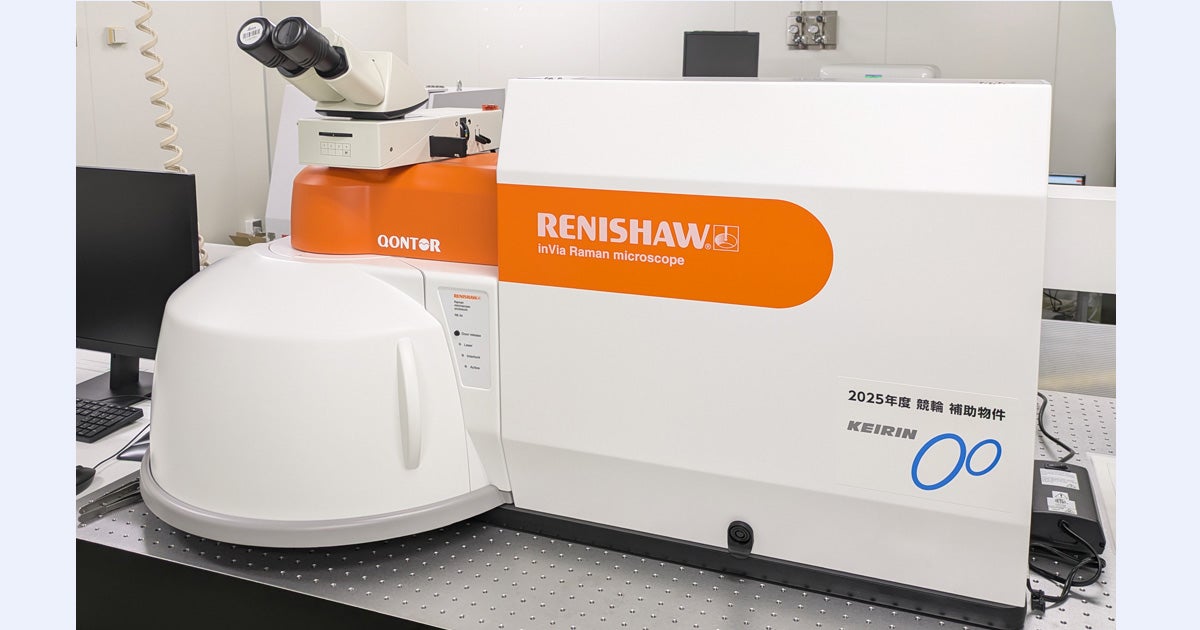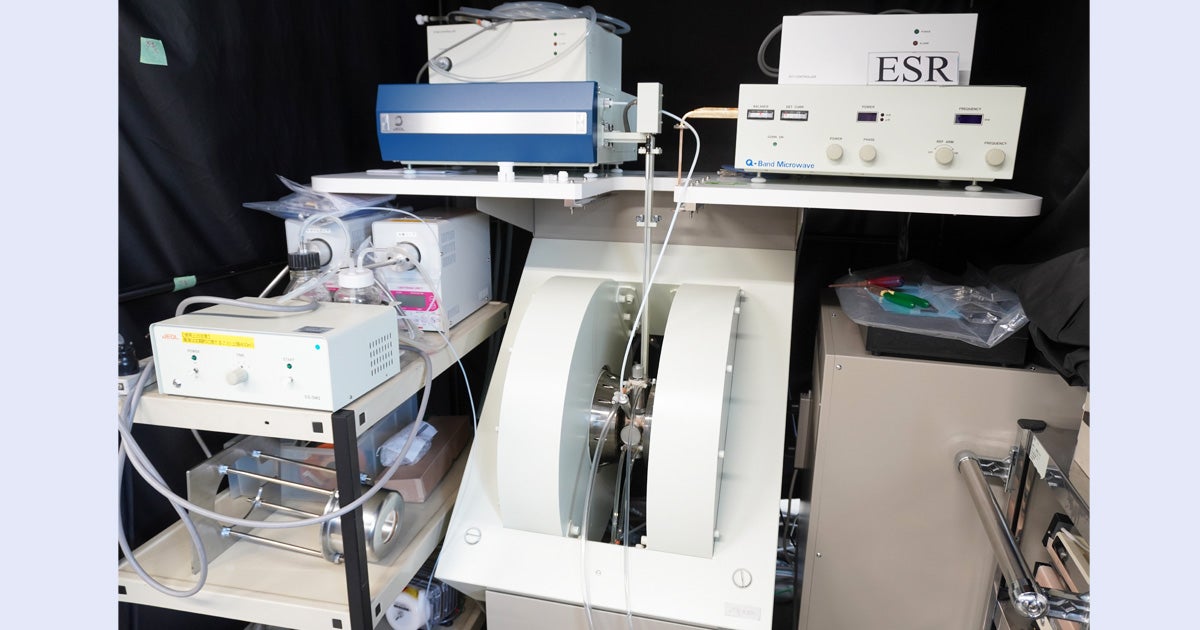X線回折装置(XRD)
公開日:2025年6月16日 最終更新日:2025年6月16日

依頼試験で使用するX線回折装置(XRD)を2024年度にリニューアルしました。本装置は、試料にX線を照射することで得られるX線回折パターン※1から、試料にどのような構造の物質が含まれているかを調べる装置です。測定対象は主に結晶性物質ですが、非晶質の物質が結晶化していないか確認する目的でも利用されています。
※1 X線回折パターン:物質にX線を照射した際に、散乱したX線が特定の方向で強めあうことを利用して得られるパターン
測定試料と測定方法
測定対象となる試料は、粉末状、シート状、塊状等の物質です。試料を装置に設置したときに、測定面(上面)が平滑・水平である必要があります。粉末試料は専用のホルダーに詰めて測定します。測定では、X線を照射するアーム(入射側)と、試料に当たって散乱したX線を検出するアーム(受光側)を動かすことで回折パターンを取得します。2つのアームを同じ角度で動かす測定(集中法)のほか、入射側アームの角度を固定し受光側アームのみを動かすことで、試料表面の情報を選択的に取得する方法があります。
.png)
化合物の特定
測定で得られたX線回折パターンから、検出されたピークの位置やその強度などの情報を取得します。その後、ピークの情報をデータベースと照合することで、試料に含まれる化合物を特定します。解析の精度を上げるためには、測定試料に含まれる元素の情報がわかっていることが望ましいです。
.png)
炭酸カルシウムには方解石と同じ化学組成(CaCO3)をもち、結晶構造が異なる霰石もありますが、X線回折法ではこれらを見分けることが可能です。
導入した装置の特徴
導入した株式会社リガク製SmartLab SEは、入射側に設置する平面多層膜ミラー(CBO-α)と高エネルギー分解能の検出器(XSPA-400 ER)により、解析に使用する回折線の強度を大きく下げることなく、回折パターンのバックグラウンドを低減した集中法の測定が可能です。Kβフィルター※2レスでのKβ線※3成分の除去や、鉄などの遷移金属を含む試料で発生する蛍光X線※4の影響を低減することが可能で、解析精度の向上が期待できます。
.png)
※2 Kβフィルター:入射X線に含まれるKα線とKβ線のうち、Kβ線を選択的に取り除くことができるフィルター。Kβフィルター法では、X線回折チャートにフィルター由来の段差が現れることで、解析に支障がでることがあります。
※3 Kβ線:X線の一種。同じくX線の一種であるKα線に由来する回折線のみを通常データ解析に使用するため、Kβ線は除去することが望ましいです。
※4 蛍光X線:X線が物質に照射されたときに、その物質から放出される二次的なX線。X線回折パターンのバックグラウンドを上昇させ、解析の精度を低下させる原因となるため、できるだけ抑制することが重要です。
おわりに
X線回折装置は、測定試料の構造に関する情報から物質を特定することができる代表的な分析装置です。化学物質の製造ラインで使用する原料や合成した材料の評価、また異物分析などのトラブル解決に活用できます。
なお、X線を利用する装置は多岐にわたるので、お問い合わせの際は「X線回折(かいせつ)」または「XRD」とお伝えください。
同じカテゴリの記事